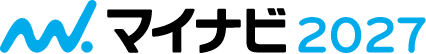キャリア・研修
- 設計/研究開発/
生産技術エンジニア - ITエンジニア
教育・研修制度
多様化する人材サービスへの
ニーズに応えます

日総工産は、日本が誇る技術者と企業の橋渡し役としてものづくりの現場を支えてきました。製造業のお客様からも日々高まるデジタル人材のニーズに応えるため、50年以上の歴史の中で培ってきた人材育成の取組みをベースにITエンジニアの事業領域を拡大しています。

人材育成の考え方

実践で必要なテクニカルスキルと
ヒューマンスキルを身に付けます
日総工産は、プログラムスキルを学ぶだけでは無く、実践で活躍できるエンジニアを育てるため、自ら調べ解決できる(自己解決能力)や質問力を高めるコミュニケーションスキルをトレーニングに取り入れております。
教育・研修の流れ

新入社員研修(1〜2週間)
入社後の新入社員研修では、社会人としての基本的な知識だけでなく、ものづくりの基礎知識も身につけていただき、日総工産で働くうえでの下地を作っていきます。職種やコースによっては、追加で専門研修を設けるケースもあります。

技術研修(3~4か月)
ITスキルを身に付けていただく為の技術研修をフルリモートで実施します。現役のIT企業の講師による実践型研修となり、未経験でも研修終了後はプログラマーとしてデビューすることが可能です。
本配属
Web開発エンジニア、サーバネットワークなどのインフラ系エンジニアとして従事していただき、プログラマーからシステムエンジニア、プロジェクトのリーダーを目指し、スキルアップしていただきます。
人材サービス企業×ITベンチャー企業
ものづくり教育で培った日総工産の教育理念をもとに、IT企業の専門カリキュラムを掛け合わせ、短期間でのエンジニア育成が可能となりました。研修中はフルリモートで時間を有効活用するとともに、居住地を制限することなく受講することが出来ます。

成長を実感したエンジニアの声

- IT系
- (院卒・理系)
ITエンジニアとしてニーズを形に。今後は幅広いプロジェクトに携わりたい。
入社の決め手としては、ITのバックグラウンドが無い未経験から始められる研修制度と研修内容に魅力を感じたことでした。実際入社しカリキュラムを受けた感想は、最初は難しく予定通りに進まないことが多かったですが、カリキュラムを進めるにつれて要領がわかり、課題をクリアすることができました。
配属後はLaravelを用いてのシステム開発に携わり、現在は詳細設計の担当フェーズでコーディング業務を担当しています。自分が考えた機能が実装できた時のやりがいと達成感は、他では感じることができません。
今後の目標としては、多数のプロジェクトを経験し、設計や要件定義などの上流工程に携わるエンジニアを目指しています。ITエンジニアを目指す学生の皆さん、当社では未経験からでも充実した研修カリキュラムが用意されていますので安心してエントリーしてください。
キャリアステップ
キャリアアップイメージ
本配属、各コース、経営層に至るまでの大まかなキャリアアップイメージをご案内します。

- POINT
-
一般的な、テスター→PG(プログラマー)→SE(システムエンジニア)→PL(プロジェクトリーダー)→PM(プロジェクトマネージャー)といったキャリアパスだけではなく、日総工産では様々なキャリアパスをご用意しています。
- ①プロジェクトマネージャーとして、メンバーやプロジェクトを束ね、開発の総責任者として予算・納期・品質に責任を持つ役割
- ②スペシャリストとして高度な業務知識や技術知識を有し、新規技術の研究や導入、レベルの高い仕様書や設計書を書ける技術者としての役割
- ③ラインマネジメントとして、組織管理・運営ならびに売上・利益に責任を持つ役割
それぞれのご要望とご経験に沿ったキャリアの選択が可能です。
※上記イメージは参考であり、配属・昇進を確約するものではありません。
キャリアを支える制度
スキルアップのために、社員が与えられた教育だけではなく、自発的に学べるしくみも整備しています。
資格取得助成制度
業務上必要な資格を社員が取得した際に会社が金銭面でバックアップする制度です。2023年4月時点では、172個の資格が助成対象となっており、社員のスキルアップを幅広く支援しています。
社内eラーニング
個の自律に向けた学習支援としてオンラインで時間や場所の制約にとらわれない学習機会のツールとしてeラーニングを完備しています。経営戦略、マネジメント、リーダーシップ、ビジネスマナーなど幅広いジャンルのプログラムがあります。
自己申告制度
将来のキャリア(希望職種や自己啓発状況など)や従業員満足度、職場環境に対する意識や意向、社員の健康状態などを会社に対して申告する制度です。
チャレンジ面談
半期に一度実施される、直属上司との面談を通じて期初の目標設定や前期評価の内容を確認しあう制度です。さらに自身のキャリアについて上司に相談する機会でもあります。